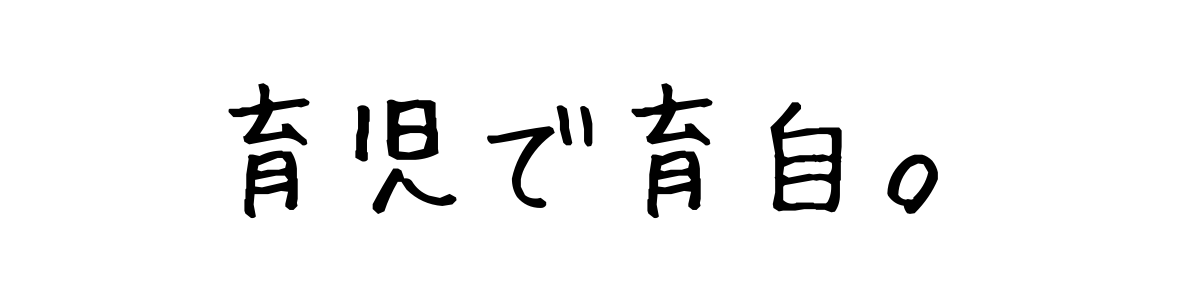『孤独と居場所の社会学 なんでもない”わたし”で生きるには』レビュー〈前編〉
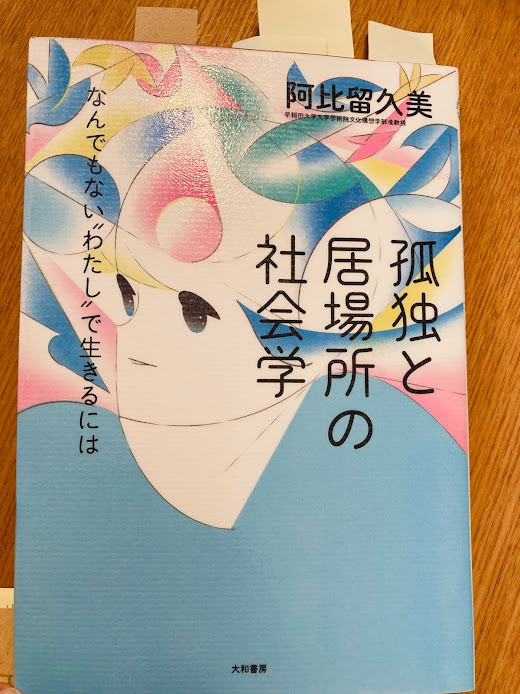
”生きづらさ”が一定以上こじれている場合、ありきたりのメンタルケアでは思うような変化がないし、悪くすると、色々やったけど結局生きづらいことに前より強い絶望感(けっきょく私はダメなんだ的な。)を感じてしまう事さえあると思います。(経験談。)
わたしは最近心理学や福祉などを大学で学び始めたのですが、これまで独学や民間スクールの講座などで断片的に学んでいた時には知らなかった心理学の面白さや広さ深さを知ってワクワクする一方で、個人の生きづらさ(特にこじれたやつ)の解消を心理学的なアプローチだけに頼るのは、ちょっと違うのではないかと考えるようになりました。
なぜなら、最初に書いたような自己否定感を強めたり、社会の課題を個人の問題にすり替えることに繋がったりする恐れがあるからです。
心の在り方の課題を解決する手段として、心理学的アプローチが有効なケースもたくさんあると思います。ただ、それらのいわば”個人的課題”と、社会の在り方のしわ寄せの結果として個人が背負っている課題とは少し切り分けて対処する必要があると思うのです。
もちろんそれらは複雑に絡み合っていて、簡単に切り離すことは出来ません。その難しいことをするためには、少なくとも、社会学や歴史を学ぶことが不可欠だとわたしは考えるようになりました。
大きな流れの中で生きている人間としての自分(と自分の心理状態)を捉えることで、今までとは違う視点を得られそうな気がしています。
そんな想いで色々と本を読む中で、今回紹介する『孤独と居場所の社会学 なんでもない”わたし”で生きるには』(阿比留久美著/大和書房出版)という本に出会いました。この本の中には、わたしが日ごろモヤモヤしながら上手く言葉に出来なかった事柄が表現されていて、読みながら「それそれ!」と何度も思いました。
また、テーマによって、マイノリティでもありマジョリティでもある自分の立ち位置を改めて客観的に確認する機会にもなりました。
この記事では、特にわたしの心に引っかかった部分をピックアップしてご紹介します。
著者の阿比留久美さんは、教育学(社会教育、青年期教育)を専門にされているそうです。ですので、この本では子どもや若者を取り巻く居場所といった事例からの考察が冒頭にあり、また、わたしはいわゆる不登校の子どもの母なので、フリースクールなどに纏わる話題にどうしてもアンテナが強く立っていることもあり、記事の始めで紹介しました。
それらは一見、不登校の子どもに限定した話題のように感じられるかもしれませんが、実は、フリースクールだけの話ではなく、子どもや若者にだけ該当する現象でもなく、居場所全般、またはマイノリティと言われる人たち関わる他の分野にも当てはまる話として読んでいただけたらと思います。
1章 なぜ居場所について考えるのか より
制度化される居場所が棄損するもの
教育学者の新谷周平によれば、居場所とは、「精神的にも物理的にも『居場所がない』マイノリティからの『言挙げ』としての意味」をもち、単一的な価値観への適応を要求する社会の中で新たな場をつくることによって、多元的な社会をひらいていく点に実践的本質をもつのだといいます。(新谷2012:233-234)
たしかに、フリースクール・フリースペースは、学校に行けなかったり、学校に行きたいと思えず不登校になっている子どもたちの居場所として登場したことで、不登校の子どもたちが確かに存在しているということを顕在化し、かれらにとって行けない/行きたいと思えない学校に適応することを強制する社会への異議申し立てをしながら、学校とは異なる場所を作ることによって、多様で多元的な社会を創造していくものでした。ですが、そうやってマイノリティからの「言挙げ」をしていくという居場所の抵抗性は、居場所という言葉を冠した活動が公的に整備することを通じて、牙を抜かれ、無効化されてしまうという側面をもちます。(後略)
『孤独と居場所の社会学 なんでもない”わたし”で生きるには P36-37』 阿比留久美著/大和書房
わたしの息子も小2からフリースクールで育っていて、通える場所に息子にフィットする居場所があることが私たち親子にとって本当に有難いと感じています。
我が家が通っているフリースクールはかなり安価な料金設定になっていますが、基本的にフリースクールの利用料金は高額なところも多く、特に都市部だと月に5万円以上することも珍しくないそうです。
その為、不登校の子どもの中でフリースクールに通えるのは、家庭にある程度の経済力がある、または先進的な自治体で行政が費用負担をしているなど、恵まれた環境にあるごく一部なのが、現状です。
公の学校に通っている子どもに対しては行政が一人当たり年間数十万単位の予算を投じていますが、何らかの理由で学校に行けない(行かない)状況になると、その子どもの教育・育ちにかかる費用は一気に家庭任せになってしまう現状があり、公的な経済的支援は絶対に必要です。
(経済面をクリアしたとしても、通える範囲にフリースクールが存在しないケースもとても多いので、お金だけの問題ではありませんが。)
でも同時に、公的な枠組みで支援されるということは、枠が苦しくてそこから出て新たな居場所を作ったはずなのに、その居場所も枠で囲われてしまわれかねない側面がある、という上記の指摘も、意識しておかなければいけないとわたしも感じています。
フリースクールも合わない子どもも当然いますし、とにかく精魂尽き果てるような体験を経て休み始めた子どもの場合、すぐに外に出て行けるエネルギーなどなく、まずは休養が必要です。
ですが、フリースクールの認知が広がったり、数が増えたりしたことによって、「学校が合わなくてもフリースクールがあるでしょ?」といった言葉かけにプレッシャーを感じたり、フリースクールさえ行けない…といった自己否定感を持ってしまったりと、まさに『枠を出てもまた新たな枠に囲われる』というような事態に直面している家族も多くいます。
それまで国は、不登校の児童生徒は学校に戻れるように指導していくという方向性でしたが、この法律には、「学校外の多様な学び場の重要性」や「(学校で疲れ切った子ども達の)休養の必要性」などが明記され、その後、登校するかどうかに囚われず中・長期的な社会参加や自立への支援が目指されるようになってきました。
これは、長い間、様々な立場の方が様々な活動をしてきたお陰で作られた法律ですし、特に不登校が登校拒否と呼ばれていた時代から比べれば大きな転換点だと思います。(但し、この法律はその作成過程での紆余曲折を受け、当初目指されていたものとは違ったものになったとのことです。その経緯に関心ある方は、こちらの文献をご参照ください。『「教育機会確保」から「多様な」が消えたことの意味』→https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku/85/2/85_150/_pdf)
この法律が出来て6年経った今でも、残念ながら、社会に(現場の先生方にさえ)その考え方が浸透したとは言えません。
でも少なくとも以後、不登校の子ども達への公的な支援の流れ、(不登校のみならず子どもの貧困対策の観点からも。)上記のように「居場所という言葉を冠した活動が公的に整備」の流れは加速していると言えます。もちろん行き場所なく困っていた人たちにとってこのことは朗報としての面は大きいのですが、上記のような側面もあり、「どのような形が真に子ども達のためになるのか?」という問いは持ち続ける必要があるとわたしは思います。
本当に実現したいことは何か
ここまで子ども・若者支援の事例を通して、居場所とは何かについて考えてきました。多くの人が居場所の重要性について考え、居場所づくりの実践をしていますが、それが政策課題として取り上げられることによる問題点も明らかになってきました。
それは、政策課題としておこなわれる居場所づくりは、「当事者が、その場所を居場所として感じ、認識する」居場所を実現しようとするものではなく、「居場所が無い人に対して、居場所という手段を提供することを通じて、様々な目標を達成させようとする」ことにもつながるということです。
もし居場所が個人の実存の問題だとするならば、「ここがあなたの居場所ですよ」と誰かに言われたとしても、そこは居場所にはなりません。「目的としての居場所」などというものはなく、結果として事後的に「この場所は自分にとっての居場所だな」と認識されるものなのです。それゆえ、居場所づくりがなされ始めたときから「居場所をめぐるメビウスの輪」のようなものが起動しだしているともいえるかもしれません。(中略)
現代人には居場所が必要だという感覚が、なんとなく共有されているけれども、その居場所という言葉を通じて、わたしたちが本当に実現したいことはなんなのか、どういう社会をつくっていきたいのかということについては空白があったり、人によって思いの違いがあったりすることがわかりました。そのような居場所をめぐる錯綜した状況について、本書では紐解いていきたいと思います。
『孤独と居場所の社会学 なんでもない”わたし”で生きるには P38-39』 阿比留久美著/大和書房
下線は引用者による。
ここで書かれている「居場所が無い人に対して、居場所という手段を提供することを通じて、様々な目標を達成させようとする」そのときの、”様々な目標”が、自然発生的な本人の希望の実現をサポートするような機能であればそれは価値があると思います。
でも、うっかりすると、”居場所”を提供することと引き換えに、社会にとって都合の良い目標が設定され、それを達成できることこそがあなたが生きていく為には必要なんだ、という有言無言の圧力をかけられ、押し付けられる場所になるとしたら…
一見、”本人の希望”という形式を取っていても、実際は”未来への不安感を煽られた結果として希望させられている”ということにもなりかねない事態を想定した記述だと推察しますし、実際にそのようなことは起こっていると、わたしは感じます。
『箱』であるところの場所を用意することそのものは、自らの力で出来る人ばかりでないことを考えれば、公的に整備することは必要だとわたしは考えています。
ただ、そこを利用するかどうかについての選択権は本人にあるし、利用出来たら〇とか、利用出来ることを目指しましょう、というような評価がついてまわるとしたら、それは”居場所”にはなり得ない。
さらには、せっかく居場所を作ったのに利用しないならその人が困っていてももはや自己責任だ、とされることがあれば、その『箱』は意味がないどころかむしろ公的な整備がされる前よりもかえって、対象となる人を苦しめることになりかねません。
ここでは、フリースクールなどが例として取り上げられていますが、構造的に同様のことが他の分野でも起こり得るでしょう。
何らかの『箱』を用意され、生きていくには〇〇を手に入れるしかない、と思い込むように誘導されたり、制度で認めてもらう代わりに何かを手放したり意に沿わないことを受け入れたりすることは、全ての人が身に覚えのあることだと思います。
実際問題として、何をするにしてもお金は必要だし、根拠となる公的な制度がなければ資金は当事者自身が調達するしかありません。もしそうなれば、個人の経済力や資金調達スキルのある人とない人では状況が著しく異なってしまうので、現状、公的な整備や財政的な支援は必要です。
ただ、その中で、制度が整うということは望ましい面だけではなくて『制度に組み込まれる』という側面を持っていると自覚的になる必要があると思います。そして、上記の小タイトルでもある『本当に実現したいことは何か』を考える。
もちろん、わたしたちは、完全な形で『本当に実現したいこと』を実現できることなんてごくわずかです。実利を取る為に組み込まれることを許容しないとならない局面は確かに多い、というかほとんどそうかもしれない。けれど、まったく無自覚なよりは少しでも選択の余地がある方がいい。
気が付いたら意に沿わないことにがんじがらめになっていて、なんでこうなっているかもよくわからない、というよりは、とわたしはおもいます。
2章 存在証明を求める社会 より
「have」ではなく「be」で自他を捉える
(前略)
わたしたちは自分自身裸のまま何もない自分では価値がないと思っているからこそ、なんでもない自分ではなくて、「〇〇大学出身のわたし」だとか「素敵なパートナーがいるわたし」といったかたちで、価値のある人間になるための様々な努力を四方八方におこなってしまいます。そして、時には「どのように生きたいか」ということよりも「どのような人間に見えるか」、「うらやましいと思われる、恵まれた人間に見えるか」ということに、非常に大きい時間を割いてしまうことさえあります。
それはいわば「have(持つ)」の思想ともいえるでしょう。「have」の思想では、特定の能力や人から羨ましがられるようなものを持っている自分であればアイデンティティが保たれます。そうでなければ、アイデンティティは不安定なままになりがちなのですが、「have」のアイデンティティではなく、「be(こういう状態である)」のアイデンティティの価値のもとで生きられたならば、人はもっと自由に、自分を肯定して生きることができるのではないでしょうか。(中略)
しかし、現代社会で「have」の存在証明をし、それによって人を評価することに慣れている現代人のわたしたちにとっては、「have」にこだわることなく「be」の存在証明で生きられること自体が、「存在証明に躍起にならず、飄々と生きることができる」という新たな特殊能力の証明になってしまうというパラドックスが存在しています。(中略)
そんながんじがらめ感のある中で、それでも生きていかなければならないところに現在を生きるわたしたちの生きづらさというのがあるのでしょう。ですがそれでも、もう少し自由になって生きる方法がないかを模索してみたいと思います。
『孤独と居場所の社会学 なんでもない”わたし”で生きるには P62-64』 阿比留久美著/大和書房
※下線は引用者による。
これは、最初に読んだ時も、今ここに書き写していても、苦笑いをしてしまうくらいこのパラドックスを常日頃わたしも感じています。
「ラクに生きている」「既存の価値観に捉われずに生きている」という、一見「be」であるところのものこそがもはや、多くの人が欲しているけれど手に入れられない『そういうことが出来る今どきなかなかない能力を持つ人』という輝ける「have」、とでも言い表わせそうです。
「be」にも評価基準が付きまとい、望ましい「be」とそうでない「be」があり、望ましい「be」の状態にいることは、最高の「have」だったりする訳ですよね。
この後に、『それでも、もう少し自由になって生きる方法がないか』への答えとなり得る方法として『異化志向』というアイディアが紹介されています。『異化志向』については、書籍を読んでいただけたらと思いますが、わたしとしては”生きづらさへの処方箋”として、理想ではあるけれども実現はかなり難しいと感じました。
ただ、わたしたちは、人と異なることの”何に”怖れを感じているのか?を考えることで、新たな視点が生まれそうな気がしています。
さて、このレビュー記事の前編はここまでとして、次回の中編では、『翻弄される女性の生き方』『自立しないとダメですか?』などの章からピックアップして、ご紹介します。
男性優位社会の中で、女性が労働市場から排除されてきた結果としての家庭への包摂や、”自立”と一口に言っても、その人の持つ属性によって自立の形は暗に外的に決められていることが、違う属性の人の間の分断の一因になるメカニズムなどについて言及されています。
続き(中編)は→コチラ